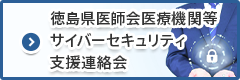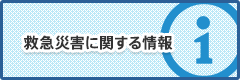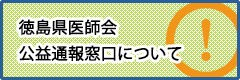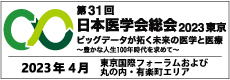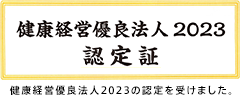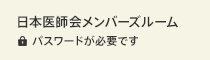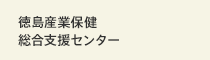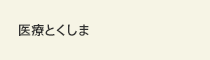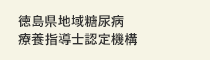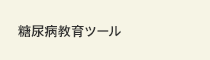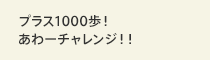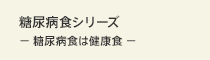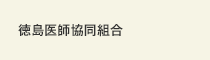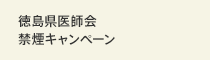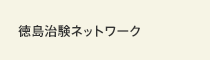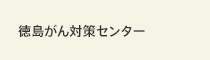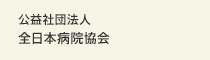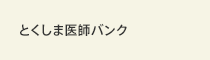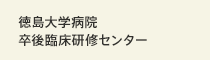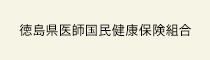- 詳細
- カテゴリ: 小児科相談
気管支喘息は子どものアレルギー疾患の代表で、症状が起こると呼吸困難を訴える病気です。また発作を繰り返すので乳幼児に呼吸困難を思わせる症状を見つけたときには喘息を疑い、早期に診断を受けて、できるだけ早く治療にかかることが大切です。
今月は子どもの喘息について症状や原因、治療、予防のお話をしたいと思います。
喘息の症状は多くが夜中や早朝に急に起こります。喘息が起こると、呼吸するときにのどの奥がヒューヒュー鳴ってひどく苦しがったり、せき込んだりします。せき込みや呼吸困難のために眠りが妨げられ、運動ができず、食欲の低下も見られます。 喘息の症状は突然起こるので発作と呼ばれます。このような喘息の症状が持続すれば成長に影響が見られることもあります。
喘息発作の特徴はヒューヒュー鳴る呼吸音にあります。この音は気管支の内側が狭くなって、ここを空気が出入りするときに聞こえます。
気管支が狭くなるのは、気管支を取りまく平滑筋が収縮するためです。さらに気管支の粘膜が腫れることや、気管支の内側にたんがからむことで、空気の通り道はさらに狭くなります。そのために呼吸音はヒューヒューに加えてゼーゼー、ゼロゼロ、ゴロゴロなどと聞こえます。
喘息の症状は自然に、または治療によって回復しますが、同じような症状が繰り返してあらわれ、慢性的な経過をとります。これが喘息の大きな特徴です。
治療を行うと狭くなった気管支が開いて症状はなくなりますが、気管支の状態は完全に元に戻ったわけではありません。少しの刺激でも気管支が収縮して喘息の症状を繰り返します。喘息の治療を始めた人は、確実に喘息が起こらなくなるまで治療を続けることが大切です。
- 詳細
- カテゴリ: 小児科相談
麻疹は症状が重い上にウイルスに対する特別有効な治療法がありませんから、普通にかかるだけでも大変な病気です。さらに麻疹には多くの合併症が見られます。これは麻疹ウイルスに侵されると抵抗力が落ちるからです。
麻疹の合併症でもっとも多いのは呼吸器系の合併症で、気管支炎や肺炎がよく見られます。とくに肺炎には麻疹ウイルスに直接侵されるウイルス性肺炎と、二次性の細菌感染による細菌性肺炎があります。
細菌性肺炎の原因菌は肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、インフルエンザ菌など一般の細菌性肺炎と同じですが、抵抗力が低下しているために重症化することがあります。
麻疹の合併症には中耳炎が多く見られます。乳幼児では耳の痛みを訴えないので、耳から膿(うみ)が出てはじめて気づかれることがあります。
さらに合併症の中でも大切なものに中枢神経系の合併症があります。麻疹脳炎と亜急性硬化性全脳炎(SSPE)です。
麻疹脳炎の発生率は麻疹患者1000人に1人とされます。麻疹発病後2週間以内に見られることが多いとされます。麻疹脳炎の死亡率は約15%、後遺症を残す率が20~40%とされます。後遺症には精神発達遅滞、けいれん、異常行動、麻痺などが見られます。
SSPEは麻疹にかかった後、10年くらいして、学童期に発病することがあります。知能傷害や行動異常、運動障害などが徐々に出現して進行します。さまざまな治療が行われますが、けいれんや不随意運動が出現、悪化してやがて死の転帰をとる怖い病気です。
SSPEの発病率は100万人に1人ですが、麻疹ワクチンを2回接種して麻疹を制圧した欧米ではほとんど見られなくなったと言われます。
日本では副作用を恐れるあまり子どもを感染症から守るというワクチン本来の目的が忘れられていることがあります。わが国のワクチン行政は欧米をはじめ全世界的には後進国になっていることを知っておく必要があります。ワクチンは誰のためでもなく、真に子どもの健康を守るためのものなのです。
- 詳細
- カテゴリ: 小児科相談
予防接種が普及して麻疹を見ることは少なくなりましたから、私たちは麻疹を過去の病気のように思い込んでいることがあります。しかし麻疹は完全に制圧されたわけではありませんから日本社会で一度麻疹が発生すれば免疫を持たない人の間に次々伝染して、麻疹が流行します。その結果、重い症状や合併症で苦しむ人が多くいることを知っておかねばなりません。
麻疹の主な症状は高熱と発疹です。発疹が出るまでの症状は発熱、咳、鼻みず、目の充血や目やになど、一般のかぜ症状と区別できないものばかりです。しかし普通のかぜに比べると症状がとても強いことが特徴です。
麻疹ウイルスは口や鼻などの気道粘膜に侵入して、侵入局所で増殖します。その後白血球を介して全身に広がり、そのため全身のあらゆる臓器の症状が出現します。 ウイルス侵入から発病までの潜伏期間は約10日です。病初期から高熱、はげしい咳や鼻みず、目やにや目の充血などが見られます。この病初期の2~3日をカタル期と呼びます。この時期には下痢などの消化器症状も見られます。
発病後3~4日すると高熱が少し下がったときに口の中、ほっぺたの内側に周辺が赤く中央が白い斑点が出現します。これがコプリック斑です。この斑点が麻疹診断の有力な手がかりになります。
一時下がったようにみえた高熱が再び上昇するときに首や耳の後ろから紅色の発疹が出現し始め、1~2日で急速に全身に広がります。この時期を発疹期と呼び、発熱は続きます。
麻疹ウイルスはカタル期から発疹期に伝染力が強く、空気感染・飛沫(ひまつ)感染・接触感染などさまざまな形態で伝染します。
その後、回復期になると熱が下がり、発疹は茶褐色の色素沈着を示し、完全に消えてしまうまでには長い時間を要します。
麻疹は約1週間の高熱をともないますから、体力のない乳幼児では合併症がなくても耐えることが難しい病気です。
- 詳細
- カテゴリ: 小児科相談
今年の春、全国的に麻疹が流行して大きな話題になりました。最近では医者の中にも麻疹を診たことがない人が多い時代になりましたが、少し前までは麻疹は誰でもかかる病気として恐れられていました。今月は麻疹についてお話したいと思います。
以前は誰でも一生に一度は麻疹にかかると考えられていました。誰でもかかるのは、麻疹ウイルスの伝染力が大変強いためです。ある地域に麻疹患者が発生すると、その地域で免疫のない人はほとんど麻疹にかかります。ワクチンのない時代に麻疹にかからないのは麻疹にかかったことのある人か、母親からの移行抗体が残っている乳児に限られました。
麻疹は数年ごとに流行していました。これは麻疹が流行すると、免疫を持たない人はほとんどが麻疹にかかり、その周辺では麻疹の免疫を持った人ばかりになり、麻疹の流行は終わります。その後数年経つと免疫を持たない子どもたちが増えて再び麻疹が流行します。このような繰り返しが続いてきました。
しかし麻疹ワクチンが普及してからは、以前のような数年ごとの流行は見られなくなりました。ただし社会全体に麻疹の免疫を持たない人の数が増えてくると、時として麻疹が流行することがあります。
従来、麻疹は1歳前後の乳児に多いものでしたが、最近の麻疹は20歳前後の成人に多く発生しています。
成人麻疹は麻疹ワクチンが普及してきたころに乳幼児期を送った世代です。この中にはワクチンを接種せずに麻疹にかからなかった人、ワクチンは接種したが免疫ができなかった人、一度獲得したワクチンによる免疫が低下した人などです。
またワクチン接種後に免疫が少し残る状態で発病する麻疹は典型的な症状がなく、正しい診断が遅れることがあります。さらに成人は行動範囲が広く麻疹にかかっても潜伏期間や病初期に仕事や旅行などに出歩くことで、麻疹ウイルスをまき散らすことがありますから注意が必要です。
- 詳細
- カテゴリ: 小児科相談
子どもの死亡事故の中で最も多いものは交通事故です。その中で最近問題になっているのが自転車事故です。自転車事故は多くが注意すれば予防できるものであり、事故の数を減らすことができるのです。
今回は自転車事故を中心にお話します。
自転車は近所を移動するのに簡単で便利な乗り物です。子どもを積んで走る姿をよく見かけます。しかし自転車は本来、車両であり車道を走行するもので、スピードも出ますからそれなりの危険性をともないます。
自転車による事故の多くは2~3歳の子どもに多く見られます。事故が起こるのは走行中がもっとも多く、次いで停車中に親が目を離したすきに転倒するものが多く見られました。
自転車事故による外傷部位ではもっとも多いのは頭部で、次に下肢です。頭部外傷の発生部位では約3分の2が側頭部で4分の1が前頭部となっています。乳幼児の側頭部はとくに骨が薄いために骨折しやすく、骨の直下を走る血管を損傷して血腫の原因になりやすいとされます。頭部外傷の中では打撲傷、皮下血腫、擦過傷など軽症のものから頭蓋(ずがい)骨骨折やくも膜下出血などによる脳損傷を起こす重傷のものまであります。また顔面を打撲して歯牙の損傷が見られる場合もあります。
事故を予防するには自転車の改良をすすめることも大切です。走行中に下肢が車輪内へ巻きこまれる事故を予防するには車輪に足が入らないようなガードをつける必要があります。頭部外傷を予防するためにはヘルメットの着用、自転車および補助いすの改良がもとめられます。
1歳前後から年齢が上がるにつれて子どもの行動範囲が広くなります。急に飛び出したり歩行が不安定で転倒したり墜落することも増えてきます。発達年齢によって起こりやすい事故が変わってきます。子どもの生理的な発達段階を理解して、事故予防の啓発にあたることが大切です。